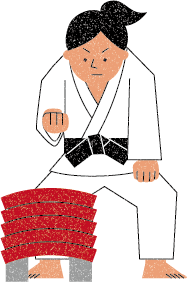嘉手納町にある首里泊手系の史跡「拳聖 喜屋武朝徳先生 碑」をご紹介します|沖縄伝統空手道振興会
嘉手納町

沖縄空手の礎を築いた偉人の1人、喜屋武朝徳の功績を称える顕彰碑が、沖縄本島中部にある嘉手納町を流れる比謝川のふもとに、静かにたたずんでいます。
喜屋武朝徳は、1870年(明治3年)に首里儀保村(現在の那覇市首里儀保町)に生を受けました。
父・喜屋武朝扶は琉球処分の最中、王府の高官として活躍した人物であり、また首里手の祖 松村宗棍に指南を受けた武人でもあった人物。幼い朝徳は6歳という早い時期から父のもとで空手の手ほどきを受けていました。
朝扶は琉球最後の王である尚泰の東京拘留に仕え、滞在していた東京に息子を呼び寄せ、朝徳は12歳からの9年間を東京で過ごし、二松学舎(現在の二松学舎大学)で三島中州から漢学を学びました。東京滞在中にも何度か沖縄を往復する中で、父の師である首里手の松村宗棍や泊手の親泊興寛(おやどまりこうかん)から空手の教えを受けていた。
26歳で帰沖後は、泊手の大家として知られる松茂良興作や親泊興寛、真栄田親雲上らの下で研鑽を積み、首里手と泊手の両方を修めた朝徳は、それぞれの特徴を深く理解し、独自の境地を開いていきました。
1910年頃からは沖縄県立農林学校や嘉手納警察署で指導を行い、1924年には那覇の大正劇場で開催された「唐手大演武大会」に参加。1930年には読谷村比謝橋に道場を構え、多くの弟子の育成に尽力しました。1937年には「空手道基本型12段」の決定にも参画し、空手の体系化にも貢献しています。
小柄で痩せた体格ながら、その実力は広く知られ、「喜屋武目小(チャンミーグヮー)」の異名で数々の武勇伝を残しています。彼の門下からは、少林流の島袋善良、少林寺流の仲里常延、松林流の長嶺将真といった、後に独自の流派を開いた著名な空手家たちが輩出されました。
この顕彰碑は、沖縄空手の発展に寄与した喜屋武朝徳の精神と技を今に伝え、空手を学ぶ者たちの心の拠り所となっています。碑を訪れる人々は、ここで空手の歴史に想いを馳せ、その精神性に触れることができるでしょう。
朝徳が築き上げた空手の伝統は、今なお多くの人々によって受け継がれ、沖縄の誇る武道文化として世界中に深く根付いているのです。
※2025年1月現在、顕彰碑のある敷地は嘉手納町管理の元、一時的に工事現場事務所として利用されていますが、史跡の見学は自由に行う事が出来ます。