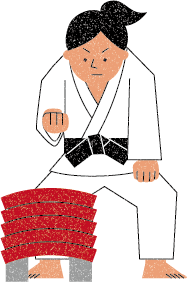沖縄本島北部の本部町にある上地流系の史跡「上地完文(うえちかんぶん)翁銅像及び顕彰碑」をご紹介します|沖縄伝統空手道振興会
本部町

上地完文翁銅像は、沖縄県本部町の八重岳桜の森公園に立つ、上地流空手道開祖を顕彰する碑です。2018年4月21日に除幕された高さ4.8メートルの銅像は、上地流空手の歴史と精神を伝える象徴的な存在となっています。
上地完文は1877年5月5日、沖縄県国頭郡本部町伊豆味に、父 完得、母 ツルの長男として生まれました。20歳の若さで中国福建省福州市に渡り、南派少林拳の重鎮である周子和の門下生となります。ここで彼は13年間にわたる厳しい修業を重ねました。
1904年、周子和から免許皆伝を受け、日本人として初めて福州市南靖で道場を開設。その後沖縄に帰郷し結婚、長男 完英(上地流2世)を授かります。
就職のため1924年に和歌山県に転出し、硬軟自在を意味する「パンガヰヌーン(半硬軟)流」空手指導を開始。1940年に流派名を「上地流」と改め流派を確立しました。
完文の空手は「眼精手捷」を理念に、龍・虎・鶴の拳を特徴とし、指先や足先を駆使した独自の技法を持っています。彼の技術は、肉体を武器化し、鋭利な槍のような攻撃力と繊細な技術の融合を追求するものでした。型の修練を重視し、「三戦」「十三」「三十六」の伝統的な型を基礎として、後に新たな型も創出されていきました。やがて長男の完英によって、上地流は国内外へと普及し、世界的に認められる空手流派へと発展していきます。
1948年11月25日、完文は71歳で逝去しましたが、その精神と技法は今も上地流空手道に生き続けています。
生誕地を正面に、終焉の地を背後に見据える「上地完文翁銅像及び顕彰碑」は、沖縄の伝統武術の偉大な開祖の功績を永遠に称え、彼の生涯と上地流空手道の精神を後世に伝える重要な文化的モニュメントとして、八重岳桜の森公園に静かに立っているのです。