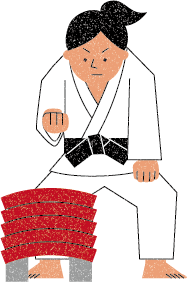宜野湾市我如古にある史跡「本部御殿墓」をご紹介します|沖縄伝統空手道振興会
宜野湾市

宜野湾市我如古に位置する本部御殿墓は、琉球王国の重要な文化遺産として知られる伝統的な亀甲墓です。
この墓は、琉球王朝第二尚氏王統第十代尚質王の第六男である尚弘信(本部王子朝平)を元祖とする本部家の墓所として、深い歴史的価値を持っています。
本部御殿墓の造営時期は、「王代記 全」の記録から1694年以降と推測されています。元祖朝平の遺骨は当初、首里末吉に安置されていましたが、康煕三三年(1694年)の洗骨の後、我如古へと移設されました。この移設に伴い、現在の墓が造営されたと考えられています。
建築様式において、本部御殿墓は初期の亀甲墓の特徴を今に伝える貴重な存在です。特に注目すべきは墓眉の緩やかな反りで、当時の建築技術の高さを物語っています。墓室内部も精巧な造りとなっており、アーチ状の天井が特徴的です。内部には奥側と壁沿いにそれぞれ一段の棚が設けられ、計十基の蔵骨器が安置されていました。
墓庭の構造も特筆に値します。石積みによって約1メートルの高低差を持つ前庭と外庭に分かれており、この設計は那覇市指定文化財「宜野湾御殿の墓」と共通する特徴です。墓庭入口から墓室正面までの高低差には、被葬者の高い身分と御殿墓としての格式を表現する意図が込められていたと考えられています。
伝承によると、本部御殿墓の敷地は二千坪という広大なものでした。墓庭入口の北側には特徴的な里道が残されており、十数メートルごとに直角に折れ曲がる独特の構造を持っています。この道はヤナムンゲーシ(邪気を払う)という沖縄の伝統的な信仰に基づいて設計された参道であると考えられています。
本部家は墓所の他にも、「本部御殿手(もとぶうどぅんでぃ)」という琉球伝統武術の継承者としても重要な役割を果たしました。特に第11代宗家となった本部朝勇(1865-1928)は、琉球王族としての高貴な血筋を持ちながら、武術の発展に尽力した人物として知られています。朝勇は幼少期から父より本部御殿手を学び、後に首里手の松村宗棍や糸洲安恒らからも指導を受けました。その卓越した技術、特に「本部の蹴り」は高く評価され、1923年には那覇に沖縄唐手研究倶楽部を設立するなど、琉球武術の普及にも貢献しました。
本部御殿墓は、2021年に宜野湾市指定文化財(史跡)として正式に認定されました。この指定は、本部御殿墓が持つ歴史的・文化的価値の高さを証明するものです。特に、首里から離れた宜野湾市我如古に本部家の墓所が築造された経緯は、当時の宜野湾間切と王族との関係を解明する上で重要な手がかりとなっています。
このように本部御殿墓は、琉球王国の建築技術、葬送文化、社会構造を今に伝える貴重な文化遺産として、また本部家を通じて武術文化とも深く結びついた歴史的遺構として、その価値が広く認められています。建築遺産としての本部御殿墓と、琉球王家の秘伝武術としての本部御殿手は、共に琉球王国の豊かな歴史と文化を現代に伝える重要な要素となっているのです。